【製造業編】マニュアルを読まない理由は? 見直しは5つの手順で改善できる!
はじめに
製造業では「現場での実践」が重要視されるため、マニュアルの管理者様から弊社に「読んでもらえるマニュアルを作ってほしい」との要望が多くあります。現場にわかりやすいマニュアル制作だけでなく、実際の業務に最適化された形で活用できれば、生産性向上や品質安定に貢献できます。今回は「マニュアルを読まない理由」とその解決策である「マニュアルの見直しは5つの手順で改善できる!」をご紹介します。
マニュアルを読まない理由は?

製造業においてマニュアルが活用されない理由はいくつか考えられます。以下のような要因が関係していることが多く見受けられます。
- 現場の経験則・暗黙知が優先される
- ・熟練者は長年の経験から得た「暗黙知」に基づいて作業を行うことが多い。
- ・マニュアルを読むよりも、先輩や上司から直接指導を受ける方が実践的で早い。
- ・「昔からこうやっているから」、「今までこの方法で問題なかった」という根強い慣習。
- マニュアルの内容が実際の作業と合っていない
- ・現場の作業が常に変化するため、既存マニュアルが実際の業務とズレている。
- ・最新の改善や効率化の工夫がマニュアルに反映されていない。
- ・現場の人からは「机上の空論」と見なされ、信頼されない。
- マニュアルがわかりにくい・使いにくい
- ・文章が長すぎたり専門用語が多かったりして、読むのが面倒。
- ・必要な情報を素早く探せないため、現場で使いにくい。
- ・写真や図が少なく、直感的に理解しづらい。
- マニュアルを参照する時間的余裕がない
- ・製造現場ではスピードが求められるため、マニュアルを見ている時間がない。
- ・一つの工程に遅れが出ると全体に影響を与えるため、特にライン作業では手元でマニュアルを確認する余裕がない。
- ・マニュアルの保管場所が作業現場から遠いところにある。
- 教育・研修がOJT中心になっている
- ・新人教育が「見て覚える」方式で進められ、マニュアルの活用が重要視されていない。
- ・先輩や上司が「仕事は体で覚えろ」という文化を持っている。
- ・そもそも、マニュアルの存在自体が十分に周知されていない。
- デジタル化されておらず、アクセスしづらい
- ・ページ数の多い紙マニュアルが保管されているだけで、現場ですぐに確認できない。
- ・デジタルマニュアルがあっても、検索性が悪く活用されない。
- ・PC閲覧仕様になっていて、現場ではタブレットやスマートフォンで簡単に閲覧できない。
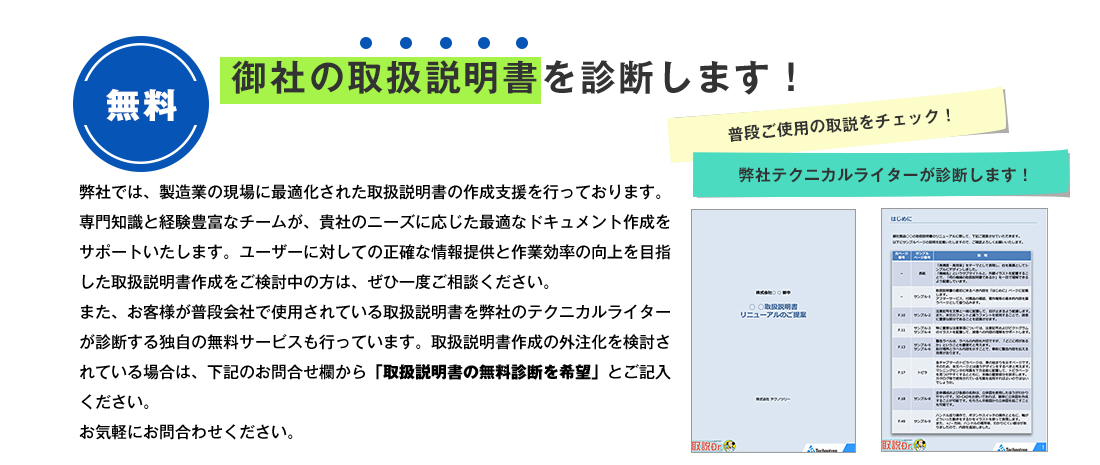
マニュアルの見直しは5つの手順で改善できる!

手順1. マニュアルの目的を明確化
マニュアルは単に作成するだけでは効果を発揮しません。たとえば、新人教育やトラブル対応の場面で適切に活用することで、作業の効率化や品質向上につながります。そのため、どのように活用するのかを明確にすることが重要です。主な目的を以下に示します。
- 作業の標準化:作業者ごとの手順の違いをなくし、一定の品質を維持する
- 新人教育の効率化:新入社員がスムーズに業務を習得できるよう支援する
- トラブル対応の迅速化:問題発生時に迅速に適切な対処ができるようにする
- 業務の効率向上:無駄な作業を削減し、生産性を向上させる
- 品質管理の強化:標準手順に従うことで製品品質を安定させる
- 法規制の遵守:業界のルールや法律に準拠した業務運営を可能にする
手順2. 使いやすい形式で提供
現場で使用されるマニュアルは、形式によって利便性が大きく変わります。状況に応じて最適な形式を選択することが重要です。
- 紙とデジタルを併用:紙のマニュアルは即時参照に適し、デジタル版は検索や更新が容易
- モバイル対応:スマートフォンやタブレットで閲覧できると、現場での利便性が向上
- インタラクティブ化:検索機能やFAQを組み込むことで、必要な情報に素早くアクセスできる
- クイックリファレンスの活用:作業員がすぐに参照できるよう、要点をまとめた簡易版を用意
- 動画マニュアルの活用:動作を伴う作業や機械の操作説明には、動画の方が直感的に理解しやすい
手順3. 定期更新とフィードバック活用
マニュアルの内容は、現場の実態に即して更新し続けることが重要です。
- 現場の意見を反映:作業者や管理者のフィードバックを定期的に収集し、実用性を高める
- バージョン管理の徹底:変更履歴を記録し、最新版が常に適用されるよう管理
- 定期的な見直し:半年~1年ごとに内容を精査し、改善点を特定
- 効果の測定と分析:マニュアルの活用頻度やエラー削減率を数値化し、改善策の検討材料に
- 最新技術の導入:業界の動向を調査し、新しい手法を適宜取り入れる
手順4. 教育・研修との連携
マニュアルを学習ツールとして初期教育と定期的な再教育に活用することで、より効果的に知識を定着させることができます。
- 研修プログラムへの組み込み:座学と実技を組み合わせ、実践的な学習を促進
- OJT(実務トレーニング)との併用:業務に直結した内容で、現場活用を習慣化
- チェックリストの活用:学習効果を確認でき、反復学習できる仕組みを導入
- eラーニングとの統合:オンライン学習と連携し、継続的なスキル向上をサポート
手順5. 現場の負担を減らす工夫
マニュアルが現場の負担にならないよう、「使いやすさ」「わかりやすさ」に配慮することが重要です。
- 視覚的に整理されたレイアウト:図解やフローチャートを活用し、直感的な理解を促進
- 要点をまとめた資料の提供:詳細版とは別に、短時間で内容を確認できるクイックリファレンスを作成
- 音声ガイドの導入:作業しながら情報を確認できる環境を整備
- 多言語対応の強化:外国人作業者向けに、翻訳版を導入
まとめ
製造業におけるマニュアルの活用には、目的を明確にし、使いやすいフォーマットで提供することが重要です。さらに、定期的な更新やフィードバックを取り入れ、教育・研修と連携することで、現場での実用性を向上させることができます。また、最新のデジタル技術(動画・インタラクティブコンテンツ・VR/ARなど)を導入することで、より効果的なマニュアル運用が可能になります。



